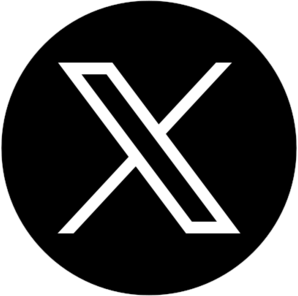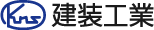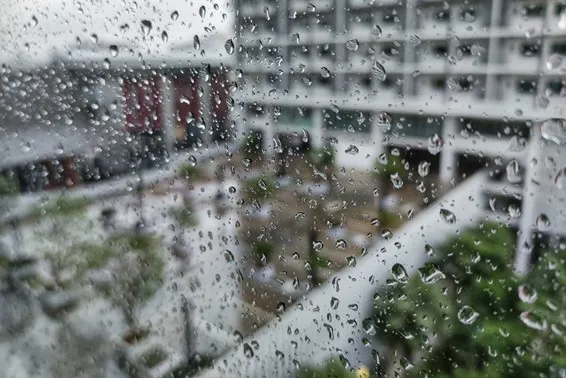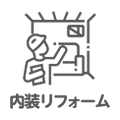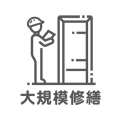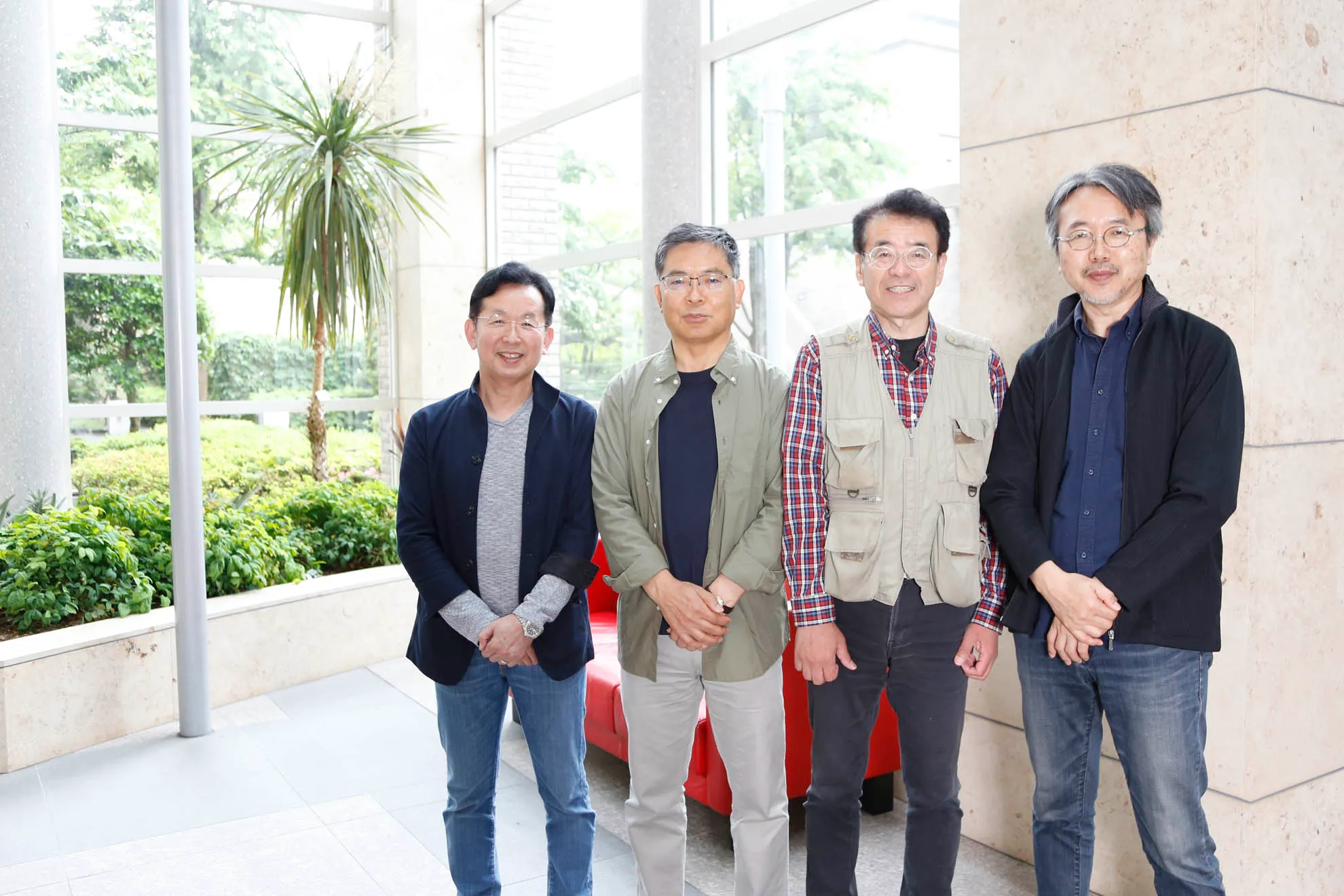タグ一覧
道路陥没の原因は水道管の老朽化? マンションで考えたい防災と大規模修繕

2025年1月、埼玉県八潮市で道路が陥没し、走行中のトラックが転落する事故が発生しました。このような道路陥没は日本各地で頻発しており、今後も起こりうる現象です。道路陥没は地域の交通や生活に重大な影響を及ぼし、人命にも関わる可能性があります。
この記事では、道路陥没事故の事例や原因、陥没が発生した場合の対処方法について説明します。
目次
1. 近年起こった道路陥没の事例とその影響とは
2. 水道管の老朽化が原因? 道路陥没が起こる理由とは
3. マンション付近で道路陥没が起こるリスク 防災と大規模修繕
近年起こった道路陥没の事例とその影響とは
近年、高度経済成長期に整備された道路や水道などのインフラ施設の老朽化に伴い、道路陥没事故が多発しています。国土交通省によれば2022年度の道路陥没事故は全国で1万件以上を超え、増加傾向にあります。
主な要因は、老朽化した道路排水施設や水道管の破損です。2020年度の調査では、全国の水道管の20.6%が法定耐用年数の40年を超えて使用されており、設備の更新が老朽化に追いついていません。
記憶に新しい事例として、2024年9月に発生した千葉県市原市の国道16号線の陥没や同2024年9月に発生した広島市の水道管破裂による陥没などが挙げられます。特に2025年1月に発生した埼玉県八潮市の陥没事故は衝撃的でした。
八潮市の道路陥没は、破損した下水道管に土砂が吸い込まれ、地中に空洞が生じたことが原因とされています。周辺地域では交通網が寸断し、近隣住民は避難を余儀なくされました。さらに人命救助や復旧工事をスムーズに進めるため、汚水を減量させるべく2週間にわたって下水の使用を控えるように呼びかけられたのです。
これらの対応は八潮市を含め中川流域下水道に関わる10以上の自治体が対象となり、大きな経済的損失が生じました。
水道は生活に不可欠なインフラの脆弱性を示しており、同様の事故は今後も起こりうる可能性があります。政府は専門家と対策を検討していますが、道路排水施設や水道管といったインフラの老朽化への対策は深刻です。
背景には、インフラの改修に掛かる膨大な費用、自治体の財政難、昨今の物価高、人件費の高騰による工事費の増大があります。大阪府の下水道事業は2018年以降、赤字経営が続き、耐用年数の50年を超過した下水道管が約1割を占めています。また、和歌山市では2014年から2023年の10年間で職員数が約1割減少しているなど職員不足に悩む自治体もあり、インフラ整備体制の脆弱さが懸念されます。
水道管の老朽化が原因? 道路陥没が起こる理由とは

道路陥没は、水道関連設備の老朽化だけでなく、トンネルなどの地下掘削工事の影響でも発生します。特に都市部では、地下空間を活用する掘削工事が盛んです。
しかし、事前調査が不十分なまま掘削が始まったり、基準に沿わない施工が行われたりすると、周辺地盤が脆弱になり、掘削上部の道路で陥没が起こるリスクが高まります。
2016年の博多駅前陥没事故や2020年に東京都調布市で発生した外環道トンネル工事現場付近の陥没事故は、地下掘削工事が要因でした。特に調布市の事例では、陥没現場周辺にある住宅の壁や基礎部分に亀裂が確認され、12軒が転居や解体を余儀なくされました。
現場付近では地下47mの深さでシールドマシンによる大規模な掘削工事が行われていましたが、事故後の調査で流動化しやすい特殊な地盤だったことが判明し、事前の調査不足が示唆されました。
一方、自然現象による陥没も発生します。2009年には北海道安平町のゴルフ場では直径約2m、深さ約5mの大きな穴が生じましたが、これは地下水の浸透による「水みち」と呼ばれる水の通り道ができ、地盤内が空洞化したためと考えられています。
道路陥没の要因は様々で、予期せぬ自然現象による発生はやむを得ない場合もありますが、地下掘削工事などの人的行為が伴う場合は事前調査を念入りに行うことが不可欠です。
マンション付近で道路陥没が起こるリスク 防災と大規模修繕

道路陥没の主な原因は、道路排水施設や水道管の老朽化が原因です。したがって、マンションの水道設備(水道管・汚水桝)の適切な管理は不可欠です。
実際にマンションの私道で陥没が発生した事例もあり、敷地内の陥没リスクについても注意が必要です。築40〜50年を経過した水道設備がある場合は、早期の改修を検討するべきでしょう。
マンションの共用部分改修には区分所有者の賛成が必要ですが、高齢者が増えたマンションでは合意形成が難しい場合もあります。
そこで、マンション敷地内の共用私道については、所在不明の区分所有者がいても工事を進められるよう国のガイドライン※が整備されました。
※民法改正と「共有私道ガイドライン」の改訂について(国土交通省)
それでは、マンション周辺で道路陥没が起こったらどうすればよいのでしょうか。
道路陥没を発見したら、まずは警察や自治体に通報しましょう。国土交通省の道路緊急ダイヤル(#9910)は、電話だけでなくSNSやアプリからも連絡可能です。ただし、マンション敷地内の共用私道など、私有地での事故は対象外となる点に注意してください。
私有地内の排水設備は下水道局の管轄外であり、マンション管理組合が管理責任を負います。そのため、敷地内で異常を発見したら、マンション管理会社や管理組合に連絡し、居住者間で情報を共有しましょう。その後、劣化調査を実施し、改修や大規模修繕を検討します。
国土交通省によると、マンションの屋外排水設備の改修の周期は24〜28年が目安とされ、完成から24〜30年経過した頃に実施される2回目の大規模修繕が適切なタイミングといえるでしょう。これは道路陥没のリスク回避にも繋がります。
居住者一人ひとりが防災計画を確認し、緊急避難ルートや避難場所を把握しておくことが大切です。日頃から事故や災害を想定した行動をシミュレーションし、いざという時に慌てずに行動できるように備えましょう。
■あわせてお読みください。
・風水害に備えた自分専用の防災計画を! 「マイ・タイムライン」の作り方
・マンションでの防災対策。一年に一度の備蓄の日に日常備蓄をチェック!
・災害に備えてマンションの防災力を強化!
・マンションの防災力を高める 大規模修繕でプラスしたい施設・設備とは
・【管理組合取材レポート】震災経験を活かしタワーマンションの防災対策向上を! 〜ライオンズタワー仙台広瀬/宮城県仙台市〜
・マンション防災 自主防災組織はあったほうがいい?
・関東大震災から100年。これを機会にマンションにおける防災対策を見直してみては?
・防災訓練にもなる「おうちキャンプ」のすすめ 災害時に役立つアウトドアグッズも!
・どうなる修理費の負担。マンションにおける責任分界点とは?
・【管理組合取材レポート】タワーマンションの排水管更新工事に挑む! 〜ザ・シーン徳川園/愛知県名古屋市(前編)〜
■この記事のライター
□熊谷皇(くまがいこう)
国立大学法人 鹿児島大学院工学研究科建築学専攻終了。専門は建築環境工学(温熱環境、省エネルギー)。国土交通省住宅の省エネ基準検討WG委員、日本産業規格JIS A 9521(2017)技術コンサル、建築環境省エネルギー機構(IBEC)・日本建築センター(BCJ)・職業能力開発総合大学校の講師、日本建築ドローン協会(JADA)WG委員を歴任。
(2025年4月21日新規掲載)
*本記事は掲載時の内容であり、現在とは内容が異なる場合ありますので予めご了承下さい。