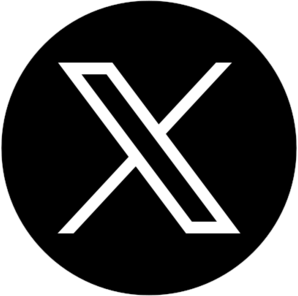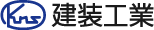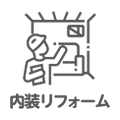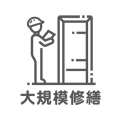タグ一覧
ベランダを片付ける! やっかいな鳥のフン対策と掃除方法(改定版)

(この記事は2021年3月に掲載した記事を更新したものです。)
ベランダの片付けや掃除をする時に、本当に困ってしまうのが鳥のフンです。特にマンションでは、スズメやカラス、ハトといった身近な野鳥によるフン害が後を絶たず、マンションの住民にとって大きな悩みの種です。
実は、鳥のフンには様々な病原体が含まれている可能性があり、ベランダにそのまま放置しておくと、私たちの健康に悪影響を及ぼすことも否定できません。そのため、鳥のフンを取り除く際には、フンが飛び散らないように十分に注意する必要があるのです。
今回は、みなさんが安心してベランダの鳥のフンを掃除できるように、その手順や注意点、そして鳥を寄せ付けないための対策について詳しく解説していきます。
目次
1. なぜ鳥のフンがそんなにやっかいなの?
2. これで安心! ベランダの鳥フン掃除の手順と注意点
3. 鳥を寄せ付けないための対策
4. 鳥の種類別! フン害を防ぐための対策
なぜ鳥のフンがそんなにやっかいなの?
気が付くとベランダの手すりや床にこびりついている鳥のフン。乾燥して固まってしまうと、なかなか落とすのは大変です。しかし、鳥のフンがやっかいな理由は、掃除のしにくさだけではないのです。
鳥のフンには、寄生虫や様々な細菌、ウィルスといった病原体が含まれている可能性があります。特に注意したいのは人にも感染する病気です。例えば、オウム病にかかるとインフルエンザのような症状が出たり、クリプトコックス症は風邪のような症状から肺疾患につながることもあります。
また、鳥のフンや羽に含まれるたんぱく質は、アレルギーの原因となることもあります。直接フンに触れないのはもちろんのこと、乾燥したフンの粒子が空気中に漂い、それを吸い込まないように注意が必要です。
さらに、鳥のフンには金属やコンクリートを劣化させる成分も含まれています。つまり、鳥のフンは建物にとっても決して無視できない存在なのです。
そして、厄介なことに鳥はフンがある場所を「安全な場所」と認識し、繰り返しやってくる習性があります。そのためフンを放置すればするほど、フン害はさらに拡大してしまう可能性があるのです。これらの理由から、ベランダで鳥のフンを見つけたら、できるだけ早く取り除くことが大切なのです。
これで安心! ベランダの鳥フン掃除の手順と注意点

鳥のフンを安全に、そして効果的に掃除するための手順と注意点をご紹介します。
●鳥のフンを掃除するときに気をつけること
・風の強い日は、フンの粒子が飛び散りやすいので作業を避けましょう。
・ほうきや掃除機を使うと、粒子が舞い上がってしまうので使用を控え、ペーパータオルなどでやさしく拭きとりましょう。
・体調が優れない時や、お子さんと一緒に作業するのは避けましょう。
・必ず使い捨てのマスクと手袋を着用しましょう。
●鳥のフンを掃除するときに使う道具
・使い捨てマスク
・使い捨てのビニール製またはゴム製の手袋
・捨てても良いぼろ布、古新聞紙、ペーパータオルなど(使い捨てできるもの)
・ゴミ袋
・水またはぬるま湯(ペットボトルやバケツに入れて用意)
・消毒用アルコール(スプレータイプ)
●鳥のフン掃除の手順
1)水で濡らしたペーパータオルなどで、フンを丁寧に拭き取ります。
2)もしフンが乾燥して固まっている場合は、水で濡らしたペーパータオルをフンに被せ、しばらく置いてください。広範囲にフンがある場合は、新聞紙を使うと便利です。
3)フンがふやけて柔らかくなったら、ペーパータオルなどで拭き取り、使用済みのペーパータオルはすぐにゴミ袋に入れます。
4)溝や隙間に入り込んだフンを取り除く場合は、古い歯ブラシを使うと効果的です。
5)仕上げにアルコール水を吹きかけて除菌します。ただし、濡れた場所にスプレーするとアルコール水の濃度が下がってしまうので、少し乾いてから吹きかけると効果的です。
もし、以上の手順でも落とせない頑固な汚れには、アルカリ性の重曹が効果的です。フンの主成分は酸性なので、重曹の粉末を汚れの上に振りかけ、少量の水を加えてペースト状にし、汚れに馴染ませてからブラシで優しくこすり洗いしましょう。
鳥のフンは、放置して時間がたつほど落としにくくなります。気が付いた時にこまめに掃除する習慣をつけましょう。
鳥を寄せ付けないための対策

せっかくベランダをきれいに掃除したら、今度はできるだけ鳥を寄せ付けないようにしたいところです。ここでは、効果的な対策をいくつか紹介します。
| 対策法 | メリット | デメリット |
| CD・ アルミホイル |
設置が簡単 | 鳥が慣れてしまう可能性がある。反射光が近所迷惑になるおそれがある。 |
| 忌避剤 | 設置が簡単 | 定期的な再設置が必要でコストがかかる。 |
| とげマット・テグス | 設置に鳥がとまるのを防ぐ | 設置箇所が多いと対応が難しい。ベランダの使い勝手が悪くなる可能性がある。 |
| 防鳥ネット | 鳥の侵入を物理的に防ぐ | 設置が大変。管理組合の許可が必要な場合がある。 |
CD・アルミホイルなどの鳥よけアイテム
よく知られている方法として、CDやアルミホイルの反射光、超音波、天敵の模型などを使って、鳥を驚かせるというものがあります。安価で設置が簡単な上に、手軽に試せるものも多いですが、鳥が慣れてしまうと効果は薄れてしまいます。反射板は、光が原因で近隣の方とのトラブルになる可能性もあるので注意が必要です。
忌避剤
鳥が嫌がる匂いや感触の薬剤で、スプレータイプ、ジェルタイプ、固形タイプなどがあります。鳥がよくとまる場所に塗ることによって効果を発揮しますが、効果を持続させるためには、定期的な使用が必要です。
手軽に使えるスプレータイプから試してみて、効果が感じられない場合には、ジェルタイプを試してみるのも良いでしょう。
とげマット・テグス
鳥は針状のものが並んでいる場所を嫌がる性質があり、寄り付きにくくなります。針の長さは5〜15cmまで様々なものがあるので、鳥の種類や大きさ、ベランダの状況に合わせて選びましょう。隙間なく設置することで高い効果が期待できますが、設置しすぎるとベランダの使い勝手が悪くなることもあります。テグスは、鳥がよく止まる手すりの上などに設置すると、鳥にとって不快な環境となり効果的です。設置しても目立ちにくいのがメリットですが、効果はテグスを設置した部分だけに限られます。
防鳥ネット
鳥の侵入を物理的に防ぐ方法としては、最も効果的といえるでしょう。しかし、隙間なく覆うには専門的な技術が必要であり、高所の作業は危険を伴います。また、マンションによっては防鳥ネットの設置が管理規約で制限されていることもあるので、事前に規約の確認が必要です。
鳥の種類別! フン害を防ぐための対策
鳥によるフン害が気になる場合は、鳥の種類とベランダにフンをする理由を知ることで、より効果的な対策を講じることが可能です。ここでは、マンション周辺で見かけることが多い鳥の例と、それぞれの生態に応じた効果的な対策について解説します。

カラス
カラスは、小枝だけでなく、針金ハンガーやビニール紐などの人工物も巣作りの材料にすることがあります。巣作りが始まる春先は、ベランダにハンガーを出したままにはせず、その他の小物類も蓋つきのコンテナなどに収納しましょう。また、カラスは雑食性で、生ごみの匂いに引き寄せられます。生ごみは蓋つきの容器に入れ、カラスの視界に入らないように工夫しましょう。

スズメ
スズメは、外敵から身を守るため、昔から人の近くに巣を作ります。屋根瓦の隙間や雨どい、換気口の隙間などに巣を作ることがあります。スズメが侵入しそうな隙間を全て塞ぐのは難しいかもしれませんが、フン害に困っている場合は、専門業者に依頼して防鳥ネットで隙間なく覆うのが効果的です。

ヒヨドリ
ヒヨドリは、植物の実や花の蜜を好みますが、花や実が乏しくなる冬場は、野菜の葉も食べに来ます。
ベランダ園芸を楽しみながらヒヨドリを寄せ付けないためには、鉢植えやプランターごとにネットをかけるのがおすすめです。

ムクドリ
ムクドリは、屋根や壁の隙間、戸袋や室外機の裏などを巣作りに選ぶことがあります。日常的にベランダを使い、こまめに掃除をしていれば、巣作りの兆候にも早く気付くことができます。人が頻繁に出入りする場所は、安心して子育てできる環境でないと認識するため、巣を作られる心配は少ないでしょう。

ハト
ハトは外敵の動きを察知しやすい、見晴らしの良い高い場所で休息する習性があり、雨風を防げるところを好んで巣を作ります。マンションのベランダは、まさにハトにとって理想的な環境といえるでしょう。まずは、ハトがとまって休む場所にテグスを張ったり、忌避剤を塗ったりして様子を見るのが良いでしょう。室外機の上などには隙間なくとげマットを設置すると効果的です。ハトは人の目につきやすい場所にも巣を作るため、巣作りの兆候を早期に発見し、阻止するためには、やはりこまめな確認と掃除が重要です。どうしても防ぎ切れない場合は、専門業者に相談し、防鳥ネットの設置を検討しましょう。
ただし、いくらフン害に悩まされているとしても、鳥を傷つけたり、捕獲したりすることは鳥獣保護法で禁止されているので、絶対にやめましょう。
今回は、マンションのベランダにおける鳥のフン対策について、その理由から具体的な掃除方法、そして予防策まで詳しく解説しました。鳥のフン害は、見た目の不快さだけでなく、健康や建物への影響も無視できません。しかし、適切な知識と対策を持つことで、この悩みを軽減し、快適なベランダ生活を取り戻すことができます。今日からできる対策を実践して、安心して過ごせるベランダを実現しましょう。もし、解決が難しいと感じたら、管理組合への相談も有効な手段であることを覚えておいてください。
■あわせてお読みください。
・鳩のフンは病気の原因に! フン害を防ぐためのベランダ鳩対策
・鳩対策にはまず相手を知ること! 鳩の生態を確認して鳥害を防ごう
・鳥害からマンションを守る! 屋上・ベランダ・ゴミ集積所におけるカラス対策
・ワカケホンセイインコが野生化して都心で大量発生! マンションでの鳴き声・フン害対策
・ムクドリは益鳥? 害鳥? マンションでできるベランダのフン害・鳴き声対策
■この記事のライター
□熊谷皇(くまがいこう)
建装工業株式会社 MR業務推進部所属
国立大学法人 鹿児島大学院工学研究科建築学専攻終了。専門は建築環境工学(温熱環境、省エネルギー)。国土交通省住宅の省エネ基準検討WG委員、日本産業規格JIS A 9521(2017)技術コンサル、建築環境省エネルギー機構(IBEC)・日本建築センター(BCJ)・職業能力開発総合大学校の講師を歴任。日本建築ドローン協会(JADA)WG委員。
(2021年3月15日新規掲載、2025年6月16日記事更新)
*本記事は掲載時の内容であり、現在とは内容が異なる場合ありますので予めご了承下さい。